診療科のご案内
循環器内科
お知らせ
冠動脈CT外来のご案内
2025年7月22日より、「冠動脈CT外来」を開始いたしました。
詳細
診療科紹介
循環器内科は主に心臓病や血管の病気を診療しております。代表的な病気として狭心症、心筋梗塞、様々な不整脈、種々の原因による心不全、末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)があります。
これらの病気には突然発症する病気もあり、当院では適切な初期治療が行えるよう、循環器専門スタッフが24時間365日体制で診療しております。
急性心筋梗塞や狭心症に対しては適切なカテーテル治療(PCI)、不整脈に対しては各種薬物療法に加えてカテーテルアブレーション、ペースメーカー治療、心室細動などの重症不整脈に対して植え込み型除細動器、重症心不全に対する心臓再同期療法と幅広い治療を行っております。
また、重症の狭心症でカテーテル治療が困難な症例や、大動脈疾患や弁膜症については心臓血管外科との連携、「ハートチーム」のもとに適切な治療を提供しております。
また、「足」に問題を抱えている患者さまについては「フットケア外来」を開設し、形成外科医、専門看護師、血管外科医とともに「フットケアチーム」で足の傷や潰瘍の治療に取り組んでいます。
各診療科の医師情報の詳細につきましては、C館1階 地域医療連携室までお問い合わせくださいませ。
主な対象疾患・検査・治療
主な対象疾患
- 狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患(虚血性心疾患)
- 様々な原因(高血圧性心臓病、弁膜症、虚血性心筋症など)による心不全
- 心房細動をはじめとする頻脈性不整脈、房室ブロックなどの徐脈性不整脈
- その他胸痛や動機症状などの胸部症状を訴える方
- 突然の失神で不整脈が疑われる方
- 下肢の症状を有する末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)をはじめ、足の壊疽や治りにくい潰瘍(フットケア外来にて対応)
実施可能な検査・治療
- 心電図
- 心臓超音波検査
- ホルター心電図
- トレッドミル
- 運動負荷エコー検査
- 下肢動脈・静脈エコー検査
- ABI(血圧脈波検査)
- SPP(皮膚還流圧)測定
- 心臓CT検査
- 心臓MRI検査
- 心臓核医学検査
- 心臓カテーテル検査
循環器内科よりご案内
東京都CCUネットワークのご案内
当院は東京都CCUネットワークの加盟施設です。
フットケア外来のご案内
平成25年6月よりフットケア外来を開設しました。
ホスピタルズ・ファイル
循環器内科 外来担当医表
外来担当医表
循環器内科よりお知らせ
- 初診の方はご予約不要ですが、待ち時間がかかります。なお、金曜日午後は再診の方のみの完全予約制のため、初診の方は承っておりません。
ご了承くださいませ。 - フットケア外来は予約制となっております。ご希望の方は循環器内科外来までお問い合わせください。 TEL: 03-3967-1181 (代表)
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 受付時間 | 初診 8:00~11:00 再診 8:00~11:30 |
初診 12:40~16:00 再診 12:40~16:30 |
| 診療時間 | 8:30~12:00 | 14:00~17:00 |
診療科や担当医により診療時間が異なる場合があります。
下記の担当医表をご確認ください。
担当医表 (循環器内科)
非常勤医師
2026年2月1日現在
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 中津 裕介 | 太田 洋 | 太田 洋 | 大塚 龍彦 | 沼尾 嘉美 | 千手 弘崇 |
| 沼田 哲也 | 原田 歩実 | 室橋 輝 | 青島 千紘 | 中津 裕介 | 沼田 哲也 | |
| 午後 | 太田 洋 | 冠動脈CT外来 | 冠動脈CT外来 |
フットケア鳥居 博子 [2/12・26] |
フットケア鳥居 博子 [2/6・20] |
|
|
ペースメーカー沼田 哲也 [2/2] |
ペースメーカー室橋 輝 [2/5] |
フットケア加納 麻由子 [2/13・27] |
||||
|
ペースメーカー千手 弘崇 [2/9・16] |
フットウェア装具診外来 | |||||
| フットケア坂元 博 |
※[ ]は診療日です。
休診・代診、診療時間変更等、外来診療担当が変更となる場合がございます。詳細は「休代診・時間変更のお知らせ」にてご確認ください。
急な変更等によりお知らせができない場合もございますので、ご了承ください。 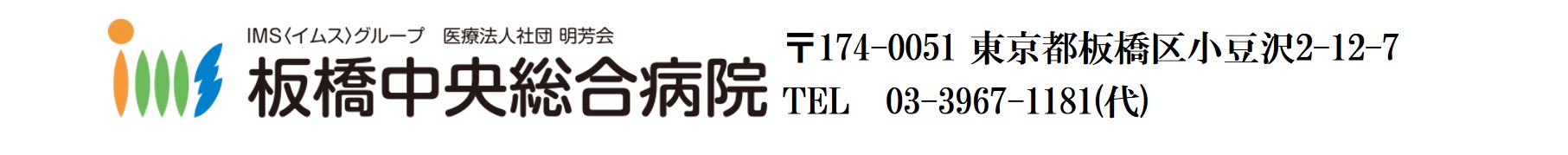
医師の紹介
常勤医師
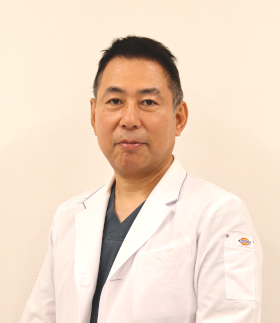
副院長/循環器内科主任部長/地域医療連携室室長 太田 洋
- 専門分野
-
- 冠動脈疾患
- 冠動脈インターベンション(PCI)
- 下肢血管内治療(EVT)
- 循環器一般
- 末梢動脈疾患に対するカテーテル治療
- 専門医認定/資格等
-
- 日本循環器学会循環器専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会心血管カテーテル治療専門医・指導医
- 日本内科学会認定内科医・指導医
- 臨床研修指導医
- 厚生労働省認定難病指定医
- 東京都身体障害者福祉法指定医(心臓機能障害の診断)

循環器内科医長 大塚 龍彦
- 専門分野
-
- 循環器一般
- 専門医認定/資格等
-
- 日本循環器学会循環器専門医
- 日本心血管インターベーション治療学会認定医
- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
- 臨床研修指導医
循環器内科医長 沼尾 嘉美
- 専門分野
-
- 循環器一般
- 専門医認定/資格等
-
- 日本医師会認定産業医
- 日本循環器学会循環器専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会認定医・血管カテーテル治療専門医
- 日本内科学会認定内科医

医員 沼田 哲也
- 専門分野
-
- 循環器一般
- 専門医認定/資格等
-
- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
- 日本循環器学会循環器専門医
- 日本不整脈心電学会不整脈専門医
- JB-POT日本周術期経食道心エコー認定医
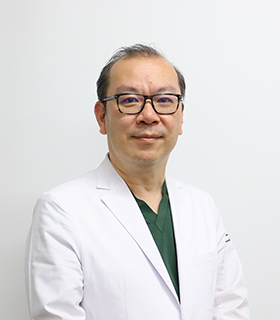
医員 中津 裕介
- 専門分野
-
- 循環器一般
- 専門医認定/資格等
-
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 日本医師会認定産業医
- 日本循環器学会循環器専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会・心血管カテーテル治療専門医
- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
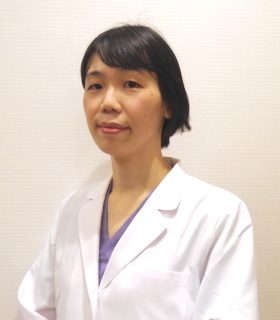
医員 青島 千紘
- 専門分野
-
- 循環器一般
- 専門医認定/資格等
-
- 日本核医学会PET 核医学認定医・核医学専門医
- 日本循環器学会循環器専門医
- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

医員 千手 弘崇
- 専門分野
-
- 循環器内科
- 総合診療科
- 専門医認定/資格等
-
- 日本内科学会認定内科医
- 日本循環器学会循環器専門医

医員 室橋 輝
- 専門医認定/資格等
-
- 日本循環器学会循環器専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会認定医
- 日本超音波医学会超音波専門医
- 日本内科学会認定内科医
- 東京都身体障害者福祉法指定医(心臓機能障害の診断)

医員 原田 歩実
- 専門医認定/資格等
-
- 日本内科学会・日本専門医機構内科専門医
解説
NCDについて
 当科は、一般社団法人National Clinical
Database(NCD)が実施するデータベース事業に参加しています。
当科は、一般社団法人National Clinical
Database(NCD)が実施するデータベース事業に参加しています。
詳しくはこちらをクリックしてください。



